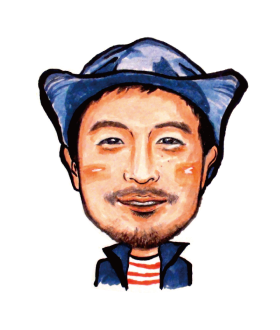多くの外国人実習生は、日本で共同生活をしています。もちろん、一人暮らしをしている実習生もたくさんいますが、「生活費の節約」という観点から、共同生活を選択するケースが多いようです。
共同生活が生むトラブルの可能性
他人と一緒に暮らす共同生活では、様々なトラブルが発生する可能性があります。「同じ国から来た実習生だから仲良く暮らせるだろう」と考えるのは安易です。同じ屋根の下で生活すれば、家族や恋人同士であっても何らかの諍いが起こるものです。ましてや、彼らは同じ国籍ではあっても、出身地はそれぞれ異なり、もともと友人関係があるわけでもありません。
弊社が関わっている受け入れ農家の方々からも、多くの事例が報告されています。
- ・夜、ルームメイトが本国の家族と電話する声が大きく、口論になった。(とても家族を大切にする実習生が多く、彼らは頻繁に電話します。)
- ・洗濯機を使おうとしたら、ルームメイトの洗濯物が残っていた。それを外に出して自分が洗濯したところ、問題になった。
- ・ルームメイトに許可なく友人を泊め、喧嘩になった。
- ・共同で購入した調味料をルームメイトが多く使いすぎ、不満が募った。
ほんの些細なことが原因でトラブルは発生します。少し気を遣えば問題にならないケースばかりですが、小さなストレスが積み重なるとコミュニケーションが不足しがちになります。その結果、自分たちで問題を解決しようとする意欲が薄れ、最終的には仕事にも悪影響を及ぼし、チームワークを乱すことになりかねません。
事前のルール作りがトラブルを防ぐ
こうした問題を防ぐために、会社と登録支援機関が間に入り、事前に共同生活のルールを作成することをおすすめします。
ただし、会社が一方的に決めたルールでは、実習生にとって身近に感じられず、守られにくいことがあります。そのため、共同生活を送る実習生の意見を反映したルール作りが重要です。実習生の価値観を考慮するだけで、多くの問題が未然に防げます。
弊社では、新しい実習生が入社するたびに、共同生活のルールを見直し、実際の生活に即した内容に更新しています。
早めの対応が円滑な共同生活のカギ
「共同生活での問題は、かなり悪化しないと表面化しない」
「自分のところはみんな仲が良さそうだから大丈夫だ」
こうした考えで油断していませんか? ルール作りの話し合いをしてみると、意外と小さなことで実習生たちが我慢していることに気づくことがあります。
早めの対策が、実習生同士の関係を良好にし、安心して働ける環境づくりにつながります。